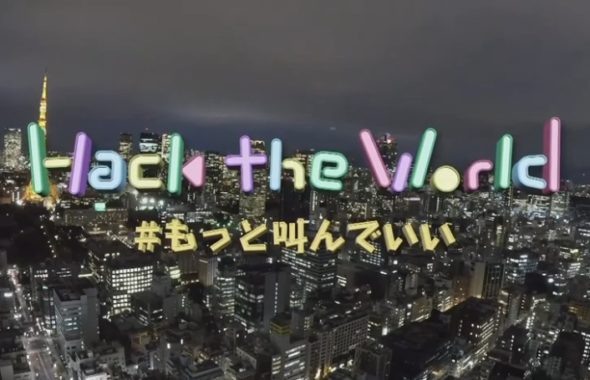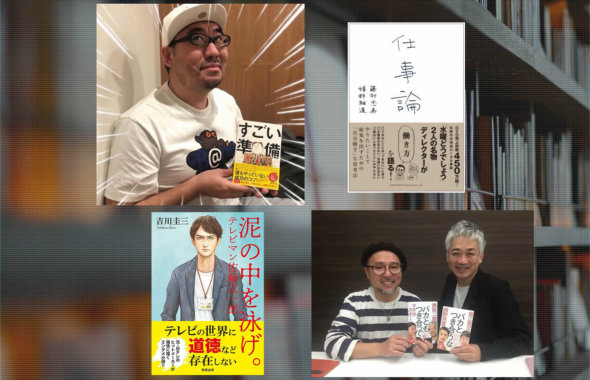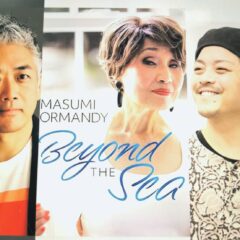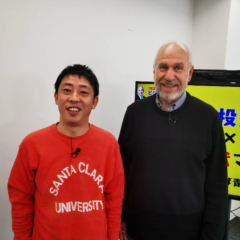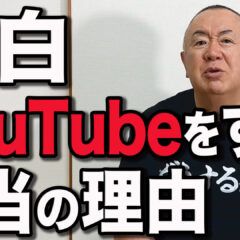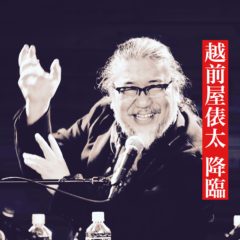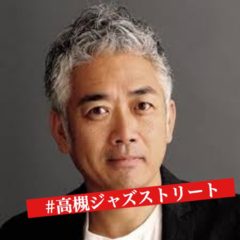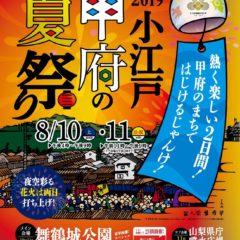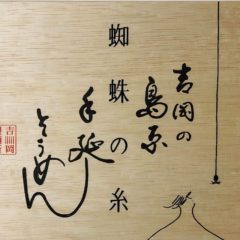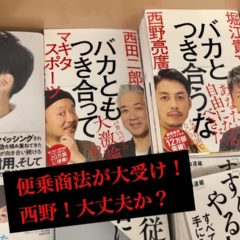「情報を持っている人が、強い。」時代の熱を感じ取り、感性を研ぎ澄ませながら、数々の「場」と「言葉」を生み出してきたプロジェクトメイカー・金杉肇さん。
音声SNS「Clubhouse」で、ほぼ毎日のように声を聞いていた金杉肇さん。
気さくに話してくれるけれど、もしClubhouseがなかったら、きっと接点はなかっただろう。話せば話すほど、その歩みの大きさに驚かされる。出てくる名前は、世界的に活躍している人ばかり。文化は大企業が作り出すものだと思っていたけれど、個人の力でも生み出せるのだと教えてくれた。
Vol.2 The code of プロジェクトメイカー 金杉肇
仕事の裏側にある『生き様』
対話を通して、その人の『輪郭』を浮かび上がらせるインタビュー・シリーズ
The Professionalism Files

◆情報をたくさん持っている人が強い‐The turning point
渋谷生まれ中野育ち。
小さい頃からませていて、母親に言わせると、大人と対等に話していたそうです。
小遣いはあんまりもらえなくて、 「早く独立しろ」とか、「自分で稼げ」と言われて育ちました。
小学校では児童会会長。中高は私立の男子校に通っていました。高校生になってからはディスコに遊びに行きたいから、部活動は辞めました。
学校が終わって、新宿の外れたところにある、最先端の音楽ばかりかける場所に、高校生の分際で通っていました。音楽好きだから、自然と詳しくなって、お店の人と親しくなれて、出入りを許されるようになりました。
大人の懐に入るのが上手かったし、大人に向かって生意気なことも散々いってました。
『情報をたくさん持っている人の方が強い』という価値観は当時培われました。
高校の美術の時間、絵を描くのは得意ではなかったけど、その代わり西洋美術史に興味を持ったんです。特に20世紀の美術史に関しては、学校の誰よりも、先生よりも詳しくなっていました。中でも1910、1920年代のフランスで、いろんなイズムが立ち上がった凄く面白い時代があるんです。パリのカフェにダリやフロイトなど尖がった詩人やアーティストが集まって、アブサンを飲みながら語り合って、新しい芸術運動が生まれた。そんな話を知ると、興奮してきちゃって。そういう尖った文化的な人が集まる場所を創りたいとディスコに通いながら、ずっと思っていたんです。
そしたら、クラブってものがあるらしい。ディスコの要素もあるけど、どうやら文化的な要素もミックスされていると聞いたんです。これは熱いぞ、見に行こうと思ってニューヨークに行ったんです。
1ドル360円の時代。「独立しろ」って言われていたから、当然親はお金を出してくれない。青山のど真ん中にあるファッション関係の人が通うチャイニーズレストランで、ホールのアルバイトをして旅費を貯めました。
北京ダックを巻きながら、写真家のアラーキー(荒木経惟)や業界の大御所たちと話す。音楽のことを聞いてくれたら、得意げに話してました。
それが特別な日ではなく、日常だったんです。
情報を持っている人は強いし、行くところに行けば、いるひとが居る。
ニューヨーク滞在中は観光なんて全くしなくて、昼はギャラリー巡り、夜はクラブを回っていました。
帰国後直ぐに、新しくできたチャイニーズレストランで「働かないか?」とスカウトされたんです。アールデコ風の、チャイニーズレストランとは思えない、めちゃくちゃかっこいいお店で「はい、働きます!」って即答しました。
「ただ、ニューヨークから帰ってきたばかりで、僕はクラブをやりたいんです。これをやらせてもらえませんか?」とクラブ文化を熱く語り、大人たちを説得しました。
実際にニューヨークまで来てもらって、クラブの遊び方を説明し、新宿の花園神社の境内の隣にクラブをオープンさせました。
自分よりも年上の文化人や横文字の肩書を持った人々が集まってきました。中には坂本龍一やマドンナの姿もありました。
情報を持っていたから、面白がってくれて。聞く耳を持ってくれる大人たちは一定数いたし、クリエイティブな人たちが喜びそうな話を分かっていました。
◆情報を得る‐My quality, My standard
これから来るぞ!って時期のアーティストは、ちょっと面白い奴がいると、ちゃんとコミュニケーションを取ってくれたんです。新進気鋭のアーティストやこれから来る業界やジャンルに目をつけて、スッと入っていくのが好きでした。
チャイニーズレストランのオープニングレセプションの招待状はアンディ・ウォホールの 雑誌
「Interview」に広告を載せて、招待客に送ったんです。その文書を書いてくれたのが当時まだ無名だった林真理子さん。みんな、何か面白い事をやる時はノーギャラでやってくれたんです
尖っている人たちと話をすると、新しいものが得られるんですよ。新しい情報も、新しい考え方も。それが楽しくて、だから文化的な人たちが集まる場所を作りたいって思っていたんです。
例えば、ファッション関係の人たちと話をする時に、ファッションの話をしてはダメで、彼らも新しい音楽を知りたいと思っているから、こちらの方が情報を持っていれば教えてあげられる。そういう立場になれば、対等ではあるけど、音楽に関してはちょっと上みたいな感じ。
だから、本当に情報って大事だし、情報の出し方とか、情報の背後にある考え方をしっかり知っていると、大人たちと対等にやっていける。
ただ、目上の人と対等に話していたけれど、逆に今は年下とも対等に話すということも出来ていると思う。コロナ禍のClubhouseでは若い子たちとよく話しました。感覚とか考え方、生の声をすごく聞きまし
◆信念・哲学‐Professional code
あるとき、友人の引っ越し祝いに写真を贈ったんです。
たまたまその場にいた写真家がそれを気に入り、プロデュースをしてくれて、銀座・ソニーギャラリーで初個展を開くことになりました。
ラッキーでした。でも、ラッキーなだけじゃない。
コンセプトを立てて、人にどう見せ、どうプレゼンするか——それを組み立てる力が、自分にはあったんです。
その業界にはその業界のルールとかお作法、文脈、言葉があるから、その言葉をちゃんと使わないといけない。
文脈
情報を取ること、その情報の背景にある考え方とか、とにかく文脈が大事。例えば、喫茶店のウエイトレスがメイドの服を着たら『メイド喫茶』になったわけ。喫茶店を再定義したら、メイド喫茶になった。だからゼロイチなんて本当はなくて、ゼロなんてないの。 喫茶店という概念に+0.1ぐらい足しただけ。あとは『メイド喫茶』って言い放つ。言葉の力って凄いから。
成功とはー
成功とはー設定した目標を確実に達成すること。例えば『ゴルゴ13』というスナイパーなら狙った目標を打ち抜くこと。掴むものではなく、辿り着くもの。ふわっとした成功を手に入れるっていうのはサクセスではなくてラッキー。
今までのプロジェクトも全て目標を設定しています。スポンサーがいたり、チームでやって行く時に、何が成功かをきちんと定義しておかないと、「成功したね」って言えない。「皆の笑顔が見たい」それはそうなんだけど、数値をクリアしないと「成功した」とは言えない。
◆夢‐Future code
本を書き続けようと思っています。
「俺はこれからどこに向かうんだろうか」常にそうゆうものと背中合わせで、考え続けることができる。この数年間、仕事をしていない時期にClubhouseに出会って、著者の方たちに出会って、編集長に出会って、本を書くことになり、本を書くっていうのは新しい人生だなって思ったんだよね。そう定義したの。だから本を書き続けようって思っているし、書きたいものがいくつかある。
次にどんな本を出すのかは、戦略だったり、出版
社との関係だったり、自分が何を書きたいのか?かけるのか?読者が何を望んでいるのか?いくつかのレイヤーが重なりあってゾーンが出来たところでやる。
それから、歴史に残るようなプロジェクトを創りたいし、成功させたい。
歴史に名を残しているプロジェクトは沢山あるけど、それが歴史として語られていない。それは一冊に纏まってないから。だからいろんな業種において、なぜそのプロジェクトが成功したのかを資料をかき集めて、エピソードを拾い上げて纏めていく作業をしたい。
(文:伊東綾子)
◇Profile
金杉 肇

起業家/プロジェクトメイカー
ドワンゴほか20社を超える企業の経営に参画。クリエイティブ、エンタメを中心にした企業の新規事業や多業種に渡るプロジェクトを数多く立ち上げる。現在、事業創出やアドバイザリー、講演や執筆など多面的な活動をしている。
著書『プロジェクト大全』
共著『マネーと国家と僕らの未来』(堀江貴文・茂木健一郎共著)